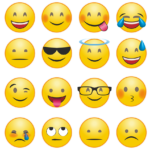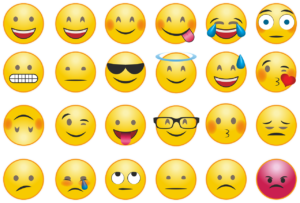世界にある国の数が196か国に対して、言語はなんと7,099種類も存在しているとされています。
そんな数多ある言語の中で、習得するのが難しい言語とは一体なんなのでしょうか?
この記事の目次
習得が難しい言語ランキングTOP5

英語を公用語にする人たちが、習得することが難しい言語ランキングです。
- 日本語
- アラビア語
- 北京語
- 広東語
- 韓国語
※引用元:BUSINESS INSIDER「英語が母国語の人にとって、最も習得するのが難しい9つの言語」
第1位は日本語でした。

僕は英語と、ほんの少しドイツ語やフランス語に触れたことがありますが、日本でライティングや校閲の仕事をしてて、日本語の方が絶対難しいよな〜と思います。
例えば僕の苗字は「後藤」ですが、「ごとう」という発音には、「五島」、「誤答」、「五等」、「五頭」、「五棟」など、山ほど他の単語が存在しています。
日本語ってこんな単語ほかにもいくらでもありますし、発音が微妙に違う、漢字は全部違うし、ひらがなにカタカナもある、謙譲語、尊敬語とかもあれば、流行り言葉に省略言葉もあって、本当に複雑な言語。
さらに、英語圏の人は発音できない音があります。僕の名前「りょう(Ryo)」がそのひとつで、小さい「や・ゆ・よ」って発音にないので、「りお(Rio)」、「りよ(Riyo)」になったり、なぜか「ろい(Roy)」になったりします。
また、人の呼び方のバラエティがとてつもなく多いのが日本語のややこしいところ。私、あたし、僕、俺、わし、わい、自分などなど。
女の子だと自分の名前で自分を呼んだり、ビジネスシーンでは小職、小生とか使う人もいます。漫画の世界では拙者、オラとかもありますよね。英語は基本「I(アイ)」だけですよ。そこだけ切り取っても全然違います。
僕の友人のバイリンガル(英語が母国語で日本語も普通に話せる)の子は、田舎に行った途端、何話してるかサッパリわからなくなると言ってましたが、それも理解できますよね。
こんな狭い国の中に異なる言葉の文化が存在し過ぎていて、日本人同士でも理解できないことがあるくらいです。外国人からすれば、相当難しいと感じるでしょう。
世界の言語ランキング(人口)TOP10
- 中国語(13億7000万人)
- 英語(5億3000万人)アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリアなど
- ヒンディー語(4億2000万人)インド、フィジー
- スペイン語(4億2000万人)スペイン、チリ、アルゼンチンなど
- アラビア語(2億3000万人)エジプト、イラク、モロッコなど
- ベンガル語(2億2000万人)バングラディシュ
- ポルトガル語(2億1500万人)ポルトガル、ブラジル
- ロシア語(1億8000万人)
- 日本語(1億2700万人)
- フランス語(1億2300万人)
僕が海外に行って知ったことは、英語・スペイン語・ポルトガル語は共通の単語があって、比較的理解し合えるということ。特にスペイン語とポルトガル語はかなり似てて、ほとんど理解できるらしい。
なので、英語のクラスで初級者クラスにいるようなスペイン人やブラジル人でも、難しい単語知ってるようなことってあるんです。
日本人からすると、中国語って似た漢字使うことがちょいちょいあるので、なんとなくわかったりすることあると思うんですが、それと同じような感覚かな?と思われます。
海外留学して英語学習した体験談
筆者はフィリピンはセブ島で1ヶ月、オーストラリアで約10ヶ月、語学学校に通って勉強し、計3年以上の海外生活をした経験があるので、その経験を基に、英語の学習について参考までに紹介します。
英語力は底辺レベルからスタート
まず、海外に到着した当時の筆者の英語レベルは非常に低く、語学学校入学時に行われるレベル分けテストでは、6段階ほどで構成されるクラスで下から2番目の成績でした。
詳しい点数とレベル分けの基準は説明がなかったですが、選択式の問題もあり、勘で回答したものも多々あったので、実質的には1番下のクラスの実力だったでしょう。
底辺レベルから脱出したが
僕は国と地域を移動しながら3つの語学学校に通いましたが、最終的には1番上のクラスに上がりました。
一般英語クラスで1番上までいけたので、その後、IELTS(アイエルツ)対策クラスというクラスに転入しました。※IELTSとは、世界基準の英語力を測るテストのひとつ。日本ではTOEICが主流ですが、英語圏の国でTOEICは基本通用しない。
在学期間が余っていたから、どうせなら他の勉強もしてみようという気持ちでの移動でしたが、帰国して英語を使って仕事をしたいとか、英語を活かして転職したい願望があったわけでもなかったので、結局テストは受けませんでしたが。
オーストラリアでは2年間、レストランやバーで接客をしていたので、学校以外でも英語を使う機会は日常的にありました。
こう見ると、「すごく成長したんだな」「きっとかなりの英語力をつけたんだろう」と思われるかもしれませんが、そんなことはありません。
僕自身が海外に行く前に思っていた、海外で勉強して帰国した人のイメージは、”ペラペラな人”。
僕は帰国した時、自分が想像していたような”ペラペラな人”とは程遠いところにいました。
海外生活終了時の英語力
日常レベルの読む・書く・聞くはできるけど、「話す」ことが全然満足にできない状態にありました。
もう少し具体的に言うと、会話のリズム、レスポンスが非常に悪いということです。
話すことはできるけど、何を話すか頭で考えて、話を組み立ててから言葉になるので、とにかく時間がかかる。
「自分ではそう思ってるだけで、本当はできるんでしょ?」
と思われるかもしれませんが、これは謙遜なしの自己評価です。
言語は結局「話す力」が肝
結局のところ言語の肝は「話せるかどうか」。これはどの言語でも共通だと思います。なぜなら、
・書けないけど話せる
・書けるけど話せない
では、「書けないけど話せる」方が圧倒的に役に立つから。
ここを理解した勉強と生活をしなければ、「英語は理解できるけど、会話はできない人」になってしまいます。特に日本人は。
以前テレビで、英語教師は英会話ができるのか?という検証をやっていましたが、話せる人はほとんどいませんでした。(話せる人ももちろんたくさんいると思いますが)
会社の昇進や就活のアピールポイントとして、TOEICの点数を示せれば良いという人ではなく、英語を話せるようになりたい人は、「話すこと」に重きを置いた学習スタンスが非常に重要となります。
筆者が話す力を伸ばせなかった2つの原因
満足に話す力を伸ばせなかった原因は、以下2つと考えています。
- 読み・書きの勉強をしていれば、話せるようにもなると勝手に思い込んでいた
- 英語環境の中にいることができなかった
1つずつ解説します。
1、読み・書きの勉強をしていれば、話せるようにもなると勝手に思い込んでいた
まず、読む・書く・聞く・話すの能力は同時に育たないということ。中でも特に「話す」はまったくの別物です。
これに気が付くのに時間がかかった。
「文法を覚え、あとは単語を覚えれば話せるようになるだろう」
これが僕の認識でしたが、これは半分正解で半分不正解。
日本の学校で勉強する時、聞くこと、話すことはすでにできる状態だから、話す力を伸ばすという概念が染み付いていないため、実感しないとわかりづらいことかもしれません。
授業を聞き、ノートを取って、ひたすら問題を解く反復作業は、紙のテストなら通用しますが、言葉を話すためには全然違うやり方が必要になってきます。
それは単純に「話す」こと。とにかく言葉を口に出すこと。これ以外ない。
記憶していても言葉にしていない単語は、会話の中で急には出てこないからです。
何か記憶した英単語が目の前に表示された時、誰しも意味は理解できると思いますが、それを1度も口に出したことがない場合、会話では不思議なくらい出てきません。
車の運転を教科書で学んだだけの状態と、実際に運転するのでは全然違うようなイメージでしょうか。
とっさの判断や瞬発力が必要な会話において、「これを伝えたいけどなんて言うんだっけ?」「どちらの言い方をした方が適しているんだろう?」と、いちいち停止するのは、ブレーキや急ブレーキを踏みまくりながら運転しているようなもの。
何回も乗って、同じ道を走っていれば、歩くように運転できるようになるのと同じように、言葉も何回も使っていれば定着して、自然と出るようになります。
話したければ、話すこと。簡単なようで意外とできません。
なぜなら日本人の多くは、「ちゃんと話せないといけない」と思う人が多いから。
欧米は罪の文化、日本は恥の文化。
「菊と刀」という本で紹介されていることです。
例えば会社の会議で、
・欧米だと、何か発言しなければ出席していないのと同じ(無言=罪)だから、発言する。
・日本だと、間違った発言をして恥をかきたくないから、積極的に発言する人は少ない。
これは実際英語学習でも顕著で、
・欧米人は文法はめちゃくちゃでも、とにかく発言するから話せる人が多い。
・日本人は正しい文法を使える人が多いけど、話せない人が多い。
僕は典型的な日本人タイプなので、話すよりテキストでのやりとりの方が断然楽にできます。
これだと、英語力がついたという実感はあまり感じられないでしょう。
2、英語環境の中にいることができなかった
僕が当時オーストラリアでお世話になっていた日本人の人で、オーストラリア人から「ネイティブよりもネイティブ」と言われるほど、英語が上手な人がいました。
その人に話を聞くと、当然最初は僕と同じように英語のことなんてまったくわからなかったし、数年は英語にずっと抵抗を持ちながら生活していたそうです。
どのタイミングから英語ができるようになったのか?
「基本ネイティブしかいない環境で3年間過ごしたら、話せるようになっていた」らしいです。似たような経歴を持つ他の日本人も、3年くらいネイティブだらけの環境で過ごしていたら話せるようになったと言っていました。
僕はネイティブの友人と過ごす時間もありましたが、日本人や同レベルの英語力の外国人と過ごすことの方が多かった。
元の英語力が低い人間が、このような勉強と生活をしていては到底満足に話せるようにはならないわけです。
ハッキリ言って、僕のような生活をするなら、スタディサプリENGLISH(新日常英会話コース)![]() などの教材で真剣に勉強すした方が、コスパ良く会話力は鍛えられるだろうと思いました。
などの教材で真剣に勉強すした方が、コスパ良く会話力は鍛えられるだろうと思いました。
海外に行けば英語力が身に付くというのは幻想です。
言語の習得にはストイックさが必須
海外生活をしている長さに応じて英語力が自然と上がることはありません。
肝心なのは、そこでどのように学び過ごすか。事実、オーストラリア在住20年超えの人でも、ほとんど英会話ができない人もチラホラいました。
言語の習得には継続的な勉強と練習が欠かせません。筋トレのようなもので、使っていなければすぐに失われます。
筆者はオーストラリアで2年生活した後、ヨーロッパで1年過ごしましたが、ヨーロッパでは日本での仕事を請け負ってフリーランス生活をしていたので、1人旅がほとんど。
英語で会話する機会はゼロに等しい状態でした。ヨーロッパで1年過ごした後、その足でオーストラリアに3ヶ月遊びに行きましたが、英語はまぁ出てこなくなっていました。
覚えたことを忘れないために、日々とにかく復習し、使う努力は絶対に必要です。
おわりに
日本語なんて複雑な言語を使える日本人は、きっと言語能力が高い。第二言語学ぼうと思ってる人は、ぜひ自信をもって勉強してください。